医療の質向上
~患者満足度の高い医療への挑戦~
ゲスト
聖路加国際病院院長
福井 次矢

ホスト
財団法人緒方医学化学研究所常務理事 佐賀大学名誉教授
只野壽太郎
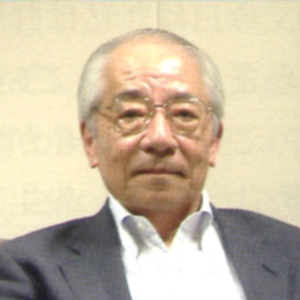
只野:先生は、足摺岬の近くの土佐清水市の中浜で生まれ育って、京都大学を卒業され、聖路加国際病院でトレーニングを受けて、New York AIDS
研究財団の稲田頼太郎先生のおられるセントルークス・ルーズベルト病院で研究をし、その後、ハーバード大学に行かれて、その教育関連病院であるケンブリッジ病院に行かれたのですね。京都大学から聖路加国際病院に行かれた経緯はどういうことだったのですか。
聖路加国際病院に行くことになったのは
福井:人との出会いです。ちょっとしたアドバイスで人生が決まっていくのだと思います。
只野:その通りだと思います。
福井:僕はもともと病理で Human Pathology をやろうと思って、京大の5年生、6年生の頃は毎週1回、病理学教室でカンファレンスに出ていました。同級生に同じように病理学に興味を持っていた坂口志文君(現京都大学再生医科学研究所教授で、先日第13回慶應医学賞を受賞)がいました。彼は実験病理をやりたいということだったのですが、僕は
Human Pathology をやりたいと思っていましたので、それだったら臨床をやったほうがいいということになりました。当時解剖の助手だった中村泰尚先生が聖路加病院でインターンをされた経験があり、また、病理の濱島義博教授から聖路加国際病院にはすばらしい先生がおられるから受験しろといわれました。そして聖路加国際病院に行くことになりました。
アメリカに留学するきっかけ
只野:聖路加国際病院のあとはアメリカに行かれましたね。
福井:そうです。2年間臨床をやっていると、病理に帰るよりも臨床をやったほうが面白そうだと思うようになりました。聖路加病院の上司にアメリカから帰ってきた先生が多く、アメリカの話ばかりでした。アメリカに行かないとまともな医者になれないという、そういうメッセージがビンビン伝わって来ましたので、どうにかして行きたいと思うようになりました。稲田先生がおられるセントルークス・ルーズベルト病院が聖路加病院と少し関係があって、コロンビア大学の教授が時々こちらに来られていました。その紹介もあって、循環器で心臓病学のいい仕事をしている先生がいるからそこはどうかということで行ったのですが、実験心臓病学を1年間やって、自分には合わないと思いました。イヌの実験が苦手で(笑)、やはり臨床をやりたいと思ったのです。僕らの頃は英語がかなり厳しくて、ECFMGにさらにVQE(Visa
Qualifying Examination)を受けなくてはならなかったのですが、それに合格していたので臨床に行くことにしました。
クリニカルフェローとしてハーバード大学に
只野:84年にハーバード大学に移られたのですか?
福井:最初はデューク大学にレジデントで行く予定だったのです。ところが手続き上のことで再渡米が延びてしまい、最終的に日野原先生より「ハーバード大学に行ったほうがいいのではないか」という助言をいただき、ハーバード大学の先生を紹介していただきました。たまたまその先生が来日していたので東京でインタビューを受けました。僕はレジデントで行くことになるものと思っていたのですが、履歴を見てクリニカルフェローのほうがフレキシブルに勉強できるだろう、という話になりました。「ライセンスはどうするのだ」と尋ねたら、「ライセンスは用意する」と言われ、「そんなことできるのかな」と半信半疑でした。でも、本当に3年間のテンポラリーライセンスを取ってくれて、レジデントでなくクリニカルフェローとして臨床をやることになりました。
日野原先生から「将来プライマリー・ケアが重要になる」と助言をいただいていたので、一般内科のグループで臨床をしました。そこでは同年代の同僚が文献を読む力が日本の同僚には考えられないほどあり、臨床研究をやればすぐNew
Engl. J. Med.やAnnals, Lancetに論文を発表していました。どこが違うのだろうと観察していると、大部分の人はハーバード大学のSchool
of Public Health(公衆衛生大学院)で統計学と疫学をしっかりと勉強していることがわかりました。僕も将来そういう医者になりたいと思っていましたし、日本もこういう医者を養成しなければ追いつかないと思ったので、ハーバード大学の
School of Public Healthで勉強して戻って来たわけです。
只野:なるほど。第9回対談の納先生も、聖路加の日野原先生に大変影響を受けられて、自分が今あるのもひとつは人の縁ですと話されましたが、「人の縁、時の運」は誰にもついて回るものと思います。先生もセントルークス・ルーズベルト病院に行き、ハーバード大学できちっとした進路の指導を受けたのがポイントでしょうね。日野原先生の「専門に狭くならないで患者さん全体を診るように勉強しなさい」という指導は大切なことですね。
アメリカの Public Health とは
只野:それから、日本ではPublic Healthというと、何か保健所の監督みたいに思われますが、向こうでは全然違うのですね。多分、行ってみなければわからなかったかもしれませんね。
福井:そう思います。日本では公衆衛生学教室というと、狭く、こじんまりした暗いところで、何か臨床とは違うことをやるイメージです。アメリカでも当初はPublic
Healthは臨床とは違うことをやるというイメージが強かったのですが、1970年代の終わりから、僕が行った80年代の最初の頃は、臨床の研究に疫学や統計学を取り入れようという機運がかなり強くなってきた、ちょうどその頃だったのです。ですから向こうでもいい人に会えたし、今でも恩師と思っている人がたくさんいます。
総合臨床との出会い
只野:総合臨床との出会いというのは……。
福井:ハーバード大学関連のケンブリッジ病院にいたときの一般内科の経験が大変勉強になりました。
只野:日本に帰って来られてから、佐賀医大に来ていただいて日本で最初の総合診療部を作り、それから京都大学に行かれ、そして聖路加国際病院に来られたわけですね。
聖路加国際病院では、最初のプロジェクトとして「医療の質を測る」ということをおやりになった。病院のQuality Indicatorというのは、アメリカやオーストラリア、イギリスなどでは国レベルでやっています。諸外国では、病院の質とか一人ひとりの医者の質などをきちっと出しているのに、日本ではこういうことは全く行われていないのですね。これを作られた目的はどこにあったのでしょうか?
福井:その前に一寸だけよろしいですか。僕は只野先生に頭が上がらなくて、先生のほうに足を向けて寝られないのです。佐賀医大に行ったとき、先生に学位の指導教官になっていただいたのですが、僕は診療そのものを研究テーマにしようと思っていました。ふつうの大学でしたら、ああいうテーマでは学位も出してもらえないし、あの時は急いでいたこともあって、英語の論文にもしませんでした。しかし、先生にサポートしていただいてどうにか物になったというか、やっていけると思いましたし、それから佐賀医大を辞めないですんだというのは、本当に只野先生のお蔭だと思っています。
診療の質を評価する理由
福井:診療そのものを評価するということですが、実はアメリカの病院での同僚のほとんどがそういう視点を持っている人たちでした。
京大の学生のときは、動物実験や細胞レベル、遺伝子レベルの研究でなければ研究じゃないというメッセージが強烈でしたので、そう思いこんでいたのですが、診療行為そのものが研究テーマになるし、降圧薬がなければどんなに素晴らしい基礎医学研究が行われても良い医療として還元されません。ですから、そういうことをやろうとなんとなく思っていたのです。そして佐賀医大で少しやらせてもらいました。
京大の教授時代、ある時、これほどたくさんの患者さんに処方されているにも拘わらず、実際に140/90mmHg以下になっている人がどれくらいいるのか誰も知らない、ということに気づきました。それで、病院の人たちに話をしたところ、京大全部のデータはとても取れないので自分の診療の範囲でやれ、と言われました。大学病院では他の診療科のデータ、病院全体のデータの収集・解析などできません。そんなことは無理だと納得はしたのですけど、血圧140/90mmHg以下にしたら合併症をかなり有意に減らせるということは研究でわかっているけれども、日常診療で実際にそれがどれくらい実践されているのかを調べない限り、研究が本当に役立ったかどうか分からないわけです。それをやるためには、いろんな診療の結果を目に見える形にしないと、誰もわかりません。最終的には、国レベルの平均寿命などに反映されているのでしょうけれど、それらの中間にある数値も明確にするべきだろうと思いました。また、病院ごと、医者ごとに、ちゃんとしたエビデンスに基づいて診療が行われているかどうかが明確になれば、皆、切磋琢磨するだろうという考えは京大にいる時からありました。京大では一介の教授ですから、何もできなかった。そのことだけが理由ではないのですが、聖路加国際病院に行ったら
Hospital Based Epidemiology もできる可能性があると考えて、京大を辞めてこちらに来ました。
電子カルテ導入時の秘話
只野:ちょうどタイミングよく、電子カルテが導入された時ですね。聖路加も2003年に佐賀医大と同時に入れたのです。あのときは日本の国立大学病院8箇所で同時に導入したのです。しかし、聖路加と佐賀医大は、使い物にならないからだめだといって運用開始を延ばしました。他の病院はスタートしたけど大変苦労した様です。聖路加は日野原先生が踏ん張って、若手の嶋田先生が中心になり作り変えました。日野原先生のところに、若手が押しかけて、運用延期を前の晩に決めたのですね。佐賀医大では、僕は退官していましたから、外から物が言えました。とにかく、こんなものを使ったら恥だと言って半年以上手直ししました。
福井:そういうことだったのですか。
只野:あの時の苦労が結局、『医療の質を測る』という本を作られる基礎資料になったのですね。

福井:そうですね。
只野:1970年代に何人かのアメリカの医者が、患者さんの顔付きと病歴を聞いただけでどのくらい診断ができるかという研究をしました。日本でこのような仕事をやる人はいないわけです。検査、検査というけども、どのくらい検査に意味があるかなど誰もやっていません。そして、患者の話をきちんと聞けば70~80%は診断できるということが証明できたわけですからね。あれはすごいことで、アメリカでは1999年に米国医療の質委員会が「人は誰でも間違える-より安全な医療システムを目指して」を報告して、そのあと2001年に「医療の質」という本ができた。あれがまさに聖路加の「医療の質を測る」国家版ですね。聖路加国際病院でやっていくなかで、これが聖路加だなあ、と思われた点がありますか。
医療情報解析室メンバーの強力なサポート
福井:僕が院長になった時、診療情報管理士が15人いたのですが、電子カルテになったら仕事の内容も変わるはずで、診療情報解析システムワーキンググループの実務部署として医療情報解析室を作って5名をそちらに異動しました。これは聖路加でないとおそらくできなかったと思います。それだけのマンパワーがあったということです。
その後、Quality Indicatorのプロジェクトを始めてからは、皆大変協力的でした。反対も多いだろうと思っていたのですが、あまりありませんでした。それに、医療情報解析室の人たちが、欧米ではこういうQuality
Indicatorのデータがあるというのを見せながら、すべての部署をヒアリングしてくれたということが素晴らしかった。もし僕一人がトップダウンでやろうとしていたら、おそらく駄目だったと思います。それを皆さんが上手くヒアリングをしてくれ、それぞれの部署に還元するというような良いデータを聞き出しました。Quality
Indicatorの本のほとんどすべての指標はそれぞれの部署の人たちが出したいと言った指標なのです。
只野:日野原先生が日本で最初に医療情報室、すなわち Medical Record Library を栗田静枝さんに作らせ、それ以来脈々と日本の診療記録をリードして来たわけですね。診療録の人達は、カルテのaudit等いろいろやっていましたが、それには限界があるわけです。紙カルテが電子カルテになってから、解析できるデータが出て来た。聖路加のレポートを見ると、例えば抗リウマチ剤の副作用とか、HbA1Cを7%未満にする診療科の割合とか、透析患者の貧血コントロール法など、臨床の質がわかりますね。これがこのレポートの一番の特長だと思います。
病院外へのインパクトは大きかった
只野:もうひとつ、先生が先ほどお話されたように、一人ひとりの方々にそれぞれインタビューをしたわけですが、そうするとやっぱり欠点も出てくるでしょうし、反対されることもあるだろうと思われたが、反対がなかったと。ホーソン効果ってありますね。Western
Electric社が、従業員同士にある程度目的意識、研究的なちょっとした目的意識を持たせて競わせると、非常に皆のモチベーションが上がってきて良くなった、ということに由来します。
福井:不良品の割合が減るという現象が観察されました。
只野:見られているということの大切さがよくわかりますね。1902年に聖路加病院を創設したルドルフ・トイスラー博士は、「この病院は生きた有機体Living
Organismだ」と言っていますが、それがこの本で非常にはっきりしていると思います。ずいぶん反響があったでしょう。
福井:ええ、いろんな病院の院長が、ぜひこういうのをやりたい、と言ってこられました。講演に来てくれとか、どうすればできるのか、といった問い合わせです。ついこの間(2008年10月20日)、国立大学附属病院の医療安全管理部門の人たち約200人に特別講演をしてきたところです。いろんなところで興味を持っている人が増えていると思います。
病院ごとのテンプレートの作成が必要
只野:僕は先生にこの本をいただいて最初に感じたのは、先生のところは2003年に入れた電子カルテの結果ですが、紙のカルテの施設がこれをやろうとすれば、大変な仕事量でしょう。また質の悪いカルテからは質の低い情報しか抽出できないことがわかれば、カルテが変わり、それが医療の質を上げることになります。われわれがいくらカルテは大切ですよと言っても、やっぱりピンと来ないのです。院長なり管理者が、きちんとこういうものをカルテの中から抽出して、病院のいいところ、悪いところがわかるっていうのだったら、これは大いに役立ちますね。来年の2月に佐賀で講演しろと言われているので、僕はこの本を使って、こんなものが作れるカルテを書けと話そうと思っています。
福井:電子カルテになっても、テンプレートを作らないとデータが取れないものもありました。テキストデータですと、データ・マイニングの手法を使ったとしても、何十%かは取れません。僕は血圧のことをやりたかったので、バイタルサインはテンプレートに記入してもらうシステムがようやくスタートしました。すごく面白いデータが出てきています。医者によって使っている処方薬の割合も種類も全然違いますし、血圧がちゃんと140/90mmHg以下にコントロールされている患者の割合もかなり異なるようです。病院ごとにどういうデータを取りたいかによって、テンプレートの作成を考える必要はあると思います。
なぜこの制度が必要か?
只野:次に、総合診療について伺いたいのですが、生涯教育のプログラムの総合医あるいは総合診療医ですが、これはまだ決まっていないのですか? どうしてこの制度が必要なのかについてお話しいただけますか。
福井:まず、臓器別専門医の視点と、一般内科や総合診療、家庭医療という視点では、医療上の役割はかなり異なります。
只野:最初からですね。
福井:専門医だけの集団では抜け落ちるいろいろな疾病や問題があります。心理社会的な問題であったり、複数の病気を持っている人の病気の治療の順番とか、ひとつの臓器だけを診る医師では実際のところ対応できない問題がたくさんあり、医療の質という観点からも、特定の臓器に片寄らない視点で診療を行う医師というのは絶対に必要だと思います。
それに加えて、今はたくさんの病気を持っている高齢者が増えているわけですから、臓器別の専門医が寄ってたかって診るという医療体制に比べ、総合医が40~50%を占めている医療体制のほうが、医療の効率性という意味からいっても絶対にいいだろうと思っています。データを出せと言われてもなかなか難しいのですが……。
只野:総合診療の必要性を考えてみると、1964年にWeedがProblem−Oriented Systemを提唱したのですが、彼は、あまり専門医制度が進んでしまって、診療科の間に隙間ができるから、総合的に患者を診られる人という意味で作ったと言っています。日本では、専門医の格が上だというおかしな風潮があって、本当は大切な普通の患者を診る医師を教育するシステムがありません。名前も付いていません。僕はWeedの精神は、診療情報を患者診療に関与した全員で共有し患者を診ることにあると思います。先生も書いておられるけど、日野原先生が、先生の循環器の患者さんの退院時に、「この人はどこに住んでいるのですか」と質問されたと。日野原先生は、カルテの講義に毎年佐賀医大に来ていただくのですが、必ずOHPで、プロブレムのところに「エレベータのない4階に住んでいる患者」というのを見せます。まさにそれが総合診療医のあるべき姿だと思うのです。
開業医の先生に対する教育
只野:先生のカリキュラムを見せていただくと、医師が通常対応する主訴は50以上あり、それに対しての対処法を書いてありますが、完璧にやろうとすると1年や2年では勉強できないですね。これから大学に入って勉強する人はいいけれど、既に開業している先生たちをどのように教育し勉強してもらうようにしたらいいのでしょうか。
福井:もしあのカリキュラムが本当に総合医の認定制度で使われるとすると、2年間の卒後研修を終えたあと3年かけて研修してもらうのが、メインの養成コースになります。こういうことを言っていいかどうかわかりませんが、大学を卒業して長年にわたって医療を支えてこられた先生方が、この新しいシステムに反対されないようグランドファーザー・クローズ(条項)を作る必要があると思います。何十時間か勉強をしていただいて、同じように認定されるというコースです。その場合には、それぞれの先生がそれなりの専門性を持ってすでに診療されていますので、専門分野以外のところをピックアップして、つまり自分の弱点は何なのかというところを、カリキュラムの中から選んで勉強してもらって、同じ総合医なら総合医という肩書きを持ってもらってはどうかと考えてはいるのですが、具体的なところまではまだ案ができておりません。
Problem Solvingで役に立つ診療支援のプログラム
只野:開業の先生を主体として、一人で診療している先生方がかなりいますね。大学病院や総合病院では、わからないことがあれば専門家が隣にいる環境ですが、それができない一人診療の先生方には、検査でも主訴でも、こういう場合はどんな病気を考える、どんな検査をすればいいのかがわかる支援システムをきちっと作って、そういう先生たちにお渡しして、一人診療でも安心して患者を診られますよ、という環境を作ることも大切でしょうね。
福井:いわゆる診療支援的なものですね。Problem Solvingで役に立つ診療支援のプログラムというか、ソフトというか、そういうものがこれから重要になってくると思います。
只野:それがあれば、先生たちも安心して診療できますね。一般の診療では、そう厄介な症例はあまり多くないですが、万が一のために必要でしょう。もうひとつは、先生が患者さんを、いつ手放すか、どこで見切りをつけるか、という臨床判断あるいは臨床決断ができるソフトが必要でしょうね。
福井:今までも、イリヤッドなどいろいろな診断のためのソフトが出てきていますが、残念ながら、臨床経験のある医師と比べると、診断精度は今のところあまり変わらないか、ややソフトのほうが劣ります。しかし、臨床経験の浅いドクターにとっては、それなりの有用性はあしますので、診療支援のソフトを使えば、今までは10年ぐらいかかってあるレベルに到達できた臨床能力を、5年ぐらいの短期間で身につけてもらうようなツールが、これからますます必要になってくると思います。
カリキュラムによる教育期間の短縮
只野:元九州大学検査医学の浜崎教授が、日立の中央研究所と組んで、救急患者を診た時に情報を入力するとその患者をどう扱ったらいいか、というソフトを作ったんです。九大でやってみると、卒後4~5年くらいまでの医者よりははるかに確実に診断したそうで。ただ、日立製作所にはそういうことがわかる人がいないために、日の目を見なかったそうで(笑)。
新潟大学医療情報部の赤沢宏平教授は工学部の出身なのですが、カルテの情報を全部コンピュータに入れて、日本では患者が少ない疾患を勉強させるシステムを作ったところ、今先生が言われたように10年の教育期間が3年ぐらいに短縮されたそうです。例えば白血病のシステムでは、それこそあらゆる種類の白血病が全部、一気に見られる。こういうものをもっと実地医家のために提供することが必要なのかもしれない。
福井:総合医のプログラムを見せると、皆さん、自分たちだってこういうことはやっていると言われるのですが、確かにちゃんとやってる人はいるかもしれないけど、それは皆さん、40歳50歳になってはじめて到達できたのであって、それまでは見よう見まねで、診断を誤ったりして患者さんに迷惑をかけてきたかもしれない。ですから、到達するまでの期間を短くするためにも、ちゃんとしたカリキュラムで勉強してもらわなければ、と思うのですけれど、なかなか皆さん賛同してくれません。
只野:僕はよく言うのですが、特に一人でやっている医師の中には、「俺のところの患者は満足している、だから自分は名医だ」と思っている医師がいます。これはその医師と合わない患者さんは来なくなるからです。集まってくる患者さんしか診ていないので本人は名医だと思っているだけなのです。そして「俺はちゃんと診ている、患者もたくさん来ているじゃないか」といっていますね。やはりエビデンスを基にして診療しないといけません。
屋根瓦方式の医師の育て方
只野:そうなってくると先生、いよいよ医者の作り方になるのですが、先生の本のタイトルはあまり良くないと思います、『なぜ聖路加に人が集まるのか』となっていますが内容とちょっと合いませんね。

福井:良くないですね。そのネーミングに私も一旦は反対したのですけど。
只野:何か格調が少し低いような気がします。研修医と医師や患者を集めているだけみたいなタイトルですね。この本には大切なことがいっぱい書いてあるので、もう少しきちっとしたタイトルにしたら、大変な本になったのにと思いますね。
いくつか話題を選んでみますと、「医師の育て方」という項がありますね。研修制度が変わったら、大学病院は考え直さなければいけないのですけど、でも考え直さないですね。なぜ聖路加国際病院、沖縄中部病院、奈良の天理よろづ相談所病院などに研修医が殺到し、勉強したいと思うのか。それを世の中に知ってもらえればと思います。以前のように、大学病院で研修し医局に入るなんてことは駄目なのだということがわかってきたのですね。先生は聖路加のやり方についていろいろ書かれていますけど、アメリカのレジデントは、1年経つと下の人を教える義務があって、上の人から絶えず教えられる。いわゆる「屋根瓦方式」ですね。あれが大切でしょうね。
福井:そう思います。聖路加病院になぜたくさん優秀な人が来てくれるかというと、多くの学生が見学に来て、聖路加病院でのやり方、1年研修をするとこんなに立派な医師になるんだ、とモデルを見て、心を動かされた学生が応募してくれるからだと思います。
只野:見学の予約も大変ですね。
福井:毎年300人ぐらい来ます。彼らが異口同音に「つい1年前に知っていた人たちが、ここで研修すると人が違ったみたいだ」というのです。「自分もそうなりたいから受験する」というのが大部分です。1年目の人は2年目を見て、全然違うと思うし、2年目は3年目、4年目を見て、やはり全然違うと言いますので、すぐ上の医師から教えてもらうことがうまく階段になっていて、良いサイクルに入っているのだと思います。それがなくて、50歳、60歳の医師のみで教えられることには限りがあります。
只野:僕はアメリカでレジデントをやってほんとに感じたのは、まず、1年上の人から徹底的に教わる。もうひとつは、10時頃になると、開業の先生が「診ておけ」といって患者を送ってきます。病歴を取り検査したりするわけですが、先生は3時ころ現れて病棟に皆を集め徹底的に質問します。日本の開業医のそんなのは見たことないから、びっくり仰天しました。ついていくのはほんとに大変だったけど、ものすごく自信がつきました。日本の教育を6年、7年受けたとしても勉強できません。これは「屋根瓦方式」の良さです。
ディスカッションをしながら患者を診る必要性
只野:もうひとつ、聖路加国際病院が大学と違うのはパブリック病棟だということです。僕はシカゴのCook County Hospital、New YorkはDown
State Medical Centerで研修しましたが、内科系病棟と外科系病棟になっているので病院全体がパブリック病棟といえます。佐賀大学病院に行くと、7階病棟の左を向けば、半分くらいがATLというわけで勉強にならない。やっぱりパブリック病棟で、いろんな患者さんをディスカッションして診ていくということがないと勉強になりません。
福井:最初から問題空間が限られているところにいたら、幅広く物を考える習慣がなくなります。
只野:ただ、聖路加は教える人が多いからいいのですよ。そうすると、日本の医療費の安さが響いてきますね。
福井:それは根本的な問題で、今でもスタッフは少ないぐらいに思っています。聖路如病院では、スタッフの医師は170~180人、初期研修医と専門研修医を合わせて120人、合計300人ですが、アメリカの大学関連病院でしたらTeaching
Staff が4~5倍はいます。
只野:電子カルテの予算を取った時、日本とアメリカの内科の教授の数と助手までの数を比較しました。ハーバードには1,400人ぐらいいるのですよ。日本の全国立大学病院でもそんなにいないです(笑い)。京都大学の内科教室は教授から助手までで40数人です。アメリカでは、ミシガン大学のような州立ですら370人で、感染症の専門家が3人もいます。もうかないっこないです。人を増やさないのなら、感染症の自動判断とか、そういう機械を作って医者に還元するから、と言ったら4億円くらい国から予算が出ました。しかし、医師数の調査をしてびっくりしたのは、ハーバード大学の一つの内科医届の医師数が日本中の全国立大学病院の内科の医者より多いのです。
福井:太刀打ちできないですね、今の日本では。
只野:やっぱり教育をきちっとして、そして医療にちゃんとお金をかける。日本はサミット7カ国で比べても、医療に対するお金の掛け方がけちけちしていますね、無駄なところに使っているからでしょうか。
福井:結局、貧しい国なのですよ。
只野:そうです。経済的にも貧しいし、為政者の頭の構造も貧しいのですよ。
福井:アメリカやイギリスは、何だかんだ言ってもやっぱり裕福な国だと僕は思います、根本的なところで。
只野:例えば病棟の仕事で比較しますと、医師のやる仕事がほんとに医師のやることだけですよ。雑用はないです。Medical Secretaryが一人いれば、医師は何十人と患者を診られるのに、日本ではそれができない。看護師にしても、看護だけに徹すればいいのに、例えば夕方になると手伝いのおばさんが帰ってしまうから、配膳までやらなきやいけないとかね。それが貧しさなのですよ。医療の貧しさというのはそういうことでもわかりますね。国に金がある・ないじやなくて、基本的な思想が貧しいと思います。
検査・薬漬けは教育により減少する
只野:そのほかに、教育をきちっとすれば、いわゆる検査漬けのようなこともなくなるのではないか。一番の問題は放射線被曝の問題だと思います。日本の癌のうち、放射線で発症したのが3%とかいうのですね。
福井:英国の研究グループが計算しています。放射線診断の被曝による癌の発生率を計算すると、日本が一番高くて3.2%、一番低いイギリスは0.6%と言われています。医療用の被曝により、日本はイギリスの5倍くらい癌になる高い。
CTが最大の原因ですね。世界のCT装置の1/4ないし1/3が日本にあると言われています。
聖路加病院でもCTのオーダーが多すぎる。単純X線でわかるようなことまでCTをとる。CTで細かいところまでわかるかもしれないけれど、臨床判断には影響を与えないようなことまで知ってどうするんだと思うのですけども、CTをとらないと不安になってしまう。
只野:ここは感染症専門の先生がいるので、抗生物質の使い方がしっかりしていますね。最初にどの抗生剤を使うとかの教育です。米国でも、レジデント等は最初はペニシリンのような基本的な薬剤しか処方できないですね。変な薬を出したらすぐに電話がかかってきて「お前、何でそんな薬を出したのか」と聞かれます。専門医がきちっと指導すれば、十分患者さんに対応できるのですが日本は、どうも尻が抜けている。
福井:その通りです。医療行政の責任も大きいと思います。人には投資できず、機械や物には投資できるような構図ができあがってしまっている。
只野:やっぱり日本は医学教育から根本的に見直さなければいけないというのが、多分、聖路加の考えていることでしょう。
ドイツ医学を守っているのは日本とロシア
只野:そこで最後に「聖路加メディカルスクール構想」についてお聞きしたいと思います。先生も本に書いておられたけど、ドイツの医者が日本に来ると故郷に帰ったみたいだと喜びますね(笑)。日本の大学のように医局制度が守られ、教授がそっくり返っているのは、ドイツに過去にはあったわけですけど。
福井:それを学んだわけですね。
只野:それを守っているのは日本とロシアでしょうか。昨年ロシアに行きましたが、ロシアでは教授はまさに皇帝です。一人の教授に3~4人くらい秘書がいて、朝9時に訪ねて行ったらテーブルにキャビアからウオツカからブランデーまで揃っている。パブロフ医科大学ですが病院全体がすべて脳の研究室なのです。車で行かなければならないような敷地の中に点々と専門診療科の病院があり、それが一つの大学病院になっています。ドイツ医学を日本より強く受け継いだといえますね。
18歳で進路を決めることの弊害?
只野:ところで、聖路加がメディカルスクールを構想されたのは、日本では18歳で自分の進路を決めてしまうというのが、一つの弊害になっているということなのでしょうか。
福井:そうですね。僕自身、4年前まで大学にいて、医師にならないほうがよいようなのが医学生になっているのをかなり見てきたものですから、よけいにそう思うのです。誤解を与えるかもしれませんが、大部分の医学生は良い医者になっているけれども、入学年齢が18歳でなければ医学部に入らなかったような人が入らなくてすむ、そういうシステムになるのではないかと思います。大学の4年間で教養を身につけて、自分の頭で考えて、本当に献身的な医師になろうと思う、そういう年齢まで待ったほうが国全体の医師養成システムとしてはいいのではないかと、そういうふうに思います。
只野:4年間リベラルアーツを学んだ人を入れれば、例えばメディカルスクールでなくともうまくいくと思うのは、鹿児島大学の丸山教授がおっしゃっていたのですが、推薦枠の中に社会人推薦枠を作ったのですね。大学を卒業してちょっとでも社会人経験した人を入れると、その人たちはすごく意欲があって、非常にいいそうです。だから育て甲斐もあるようです。
私は佐賀にいた頃を思い出すのですけれど、最初の頃の推薦入学は優秀な学生が来ました。第1回ぐらいには。例えば、神戸銀行から世界銀行に出向した人がいまして、発展途上国に医療品を分配する仕事をやっていたが、フランスやアメリカは医師が担当で、アフリカのどこはどうだとかをよく知っているそうです。とてもじゃないけど、そういう人達と医療のディスカッションをしてもかなわないので、医者になってもう一度世界銀行でそういう仕事をやりたいと入って来た人がいました。もう一人は住友電工から来ました。この人は、半導体の設計をやらされていたのですね。脳の構造みたいなパターンの設計ですが、どうも工科系より、文科系で碁を打ったりする人のほうがはるかにパターン認識力が優れていいということで勉強し直しに来ました。
日本の医療を変えるには
只野:このメディカルスクール構想はこれからの日本の医療を基本から変えると思うのですけど。
福井:最大の強みは医師になるモチベーションですが、もう一つはリベラルアーツです。僕がボストンにいた時、僕の恩師はハーバード大学で専攻したのは歴史で、それからメディカルスクールを出た人でした。だから歴史にはすごく詳しかった。またある人は文学を勉強してから医師になったなど、ハーバード・メディカルスクールでは7割ぐらいの学生のバックグラウンドが理系ではないと伺いました。僕は、良い医師になるためには、理系のみに突出した人はあまりふさわしくないと思っています。
また、いろいろなバックグラウンドを持っている人たちを集めた教育の方法として、最近ではチーム・ベースド・ラーニングというやり方があります。4年制の大学を出て、様々なバックグラウンドを持っている学生の集団でないとできないような質の高いカリキュラムがどんどん開発されています。そういう新しい方法を使って臨床医を作れば、おそらく、高校卒業生を対象にした医学教育カリキュラムで作られる臨床医とは違ってくるはずですし、よりよい臨床医を作れる可能性が高い。つまり、モチベーション・プラス・カリキュラムによって、今までの医師とは違った医師ができるのではないかと思っています。
只野:アメリカの場合は、 MCAT(Medical College Admission Test)というのですが、テストよりも徹底的な面接ですね。「ハーバード大学医学部」という本を読むと、何ヵ月もかけて何回も会いに行って、自分が医者に向いているのか、そして向こうもこの人が入ったらどんな医者になれるのか、ということを徹底的にお互いに議論して入って来る。こういうことが必要です。
デューク大学の実状
只野:先生、デューク大学のシンガポール・メディカルスクールはもう実際に始まっているのですか?
福井:ええ。ついこの間も教育の責任者に日本に来てもらって、レクチャーしてもらいました。2007年8月に第1期の26人を入学させ、2008年8月の第2期生からは50人に増やしたそうですが、インタビューをしっかりやって、入学者全員が大変優秀だと聞いています。数年前、マクマスター大学に行った時、応募者のインタビューの仕方について話を聴きました。長い期間をかけて何回かやるのでしょうが、最後のところは、受験生がオスキー(OSCE)みたいに診察室を10箇所回るというのです。各部屋に数人のインタビュアーがいて、そこでインタビューを受ける。日本でやるみたいな1回だけ10分といったインタビューとは全く違う。Admissions
Officeも日本と違ってスタッフが豊富ですね。日本ではOA入学制度とか言っていますけれど、一人や二人の事務官をおいて、それで担当の教授にやれと言われてもできないですよ。
只野:やはり豊富に人とお金をかけなければね。今の高校からのシステムを否定するわけではなくて、そういうルートもいいし、一方でメディカルスクールも作れば、自然にどちらがいいかわかってくるわけです。日本の役所は長期的に物を見られませんね、文科省も寺脇さんの時代は非常に興味を持っていたけれど、人が変わると途端に何も出なくなったりする。これでは長い目での日本の国家を作るということにはならないと思うのです。
今日はあまり長い時間お話できませんでしたが、日本の医療の将来の形を一つの私立病院である聖路加で作っているということを、この対談で皆さんに読んでいただいて、参考にしていただき、良い医療をしてもらえるようになればと思います。どうもありがとうございました。
福井:ありがとうございました。
参考文献
1)福井次矢:病歴・診察・迅速検査データの有用性:胸痛患者の診断プロセスにおける定量的評価,日本公衆衛生雑誌,37(8):56975(1990)
2)聖路加国際病院院長福井次矢監修,聖路如国匿病院QI委員会編集.Quality Indicator「医療の質を測る」聖路加国際病院の先端的試みVol.1,
インターメディカ(2007年12月)
3)聖路加国際病院院長福井次矢監修、聖路加国際病院QI委員会編集、Quality Indicator「医療の質を測る」聖路如国際病院の先端的試みVol.2,
インターメディカ(2008年10月)
4)米国医療の質委員会/医学研究所著,人は誰でも間違える-より安全な医療システムを目指して-日本評論社(2000年)
5)米国医療の質委員会/医学研究所著,医療の質 谷間を越えて21世紀システムへ、日本評論社(2002年)
6)聖路加国際病院院長福井次矢,なぜ聖路加に人が集まるのか,光文社,東京,2008